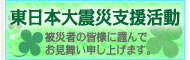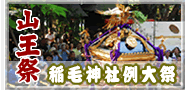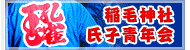和嶋弁財天と曲水連歌碑
 和嶋弁財天
和嶋弁財天
 曲水連歌碑
曲水連歌碑
かって、稲毛神社の境内には大きな弁天池があり、その中央の島に弁財天が祀られていました。その池から、現在の第一京浜国道(上り線)のあたりを多摩川方向に幅1.5メートルほどの小川が流れていました。荘園時代の堀の跡だったと思われます。
「和嶋弁財天」と呼ばれるこの社は、江戸時代には文芸の守護神として近郷の人々の崇敬篤く、種々の信仰的文化的催しが行われていました。特に、神池から流れ出る小川のほとりで行われた「曲水の宴」は優雅なものであったと伝えられています。
その曲水の宴の主催者たちが幕末に建てた2基の歌碑があります。
桜かげうつる和嶋の水の面は 音なき花の浪ぞよりくる (弘化4年・1848年) おのづから花の光し妙なれば 朧月夜もおもしろきかな (岩田専永・年代不詳)
「江戸名所図絵」に描かれていたこの神池は戦後埋められ、隣接する市の公園に近代的な池として甦っています。弁天社は今もほぼ昔の位置にあって、その前には宝暦6年(1756)に奉納された手水鉢があります。
佐藤惣之助「祭の日」詩碑
祭の日は佳き哉
つねに恋しき幼き人の
あえかに粧ひて
茜する都の方より来る時なり・・・
(詩の全文を読みたい方 こちら へ)
〈碑陰のことば〉
誰にとっても、幼い日の思い出は懐かしく美しく心に残るものである。旧川崎宿の本陣佐藤家に生まれ育った詩人佐藤惣之助は郷土をこよなく愛し、文筆生活に入ってからも「川崎の惣之助」を看板のようにしていた。そんな惣之助にとって、幼い日の鎮守の祭りはひとしお思い出深いものであった。
その日は、晴れ着姿でやってくる横浜の親類の女の児を頭髪を刈って迎え、共にレモン水をなめ見世物を観て楽しむことができたからである。その幼い客こそ、のちの花枝夫人その人であった。惣之助夫妻の生誕百年にあたり、川崎今昔会はゆかり深いこの鎮守の境内に、惣之助の思い出の詩「祭の日」の一節を抜き出し、嗣子沙羅夫氏の揮毫により詩碑として建立し、記念とする。
平成二年十二月三日 川崎今昔会 古江亮仁 識す
芭蕉句碑

秋十とせ 却って江戸をさす故郷 (芭蕉)
芭蕉没後三百年 圓鍔 勝三書 印
〈 碑陰のことば 〉
この句は芭蕉の最初の旅日記「野ざらし紀行」巻頭二番目の句である。
これが唐の詩人賈島の「桑乾ヲ渡ル」によることは分明である。
客舎并州スデニ十霜
帰心日夜咸陽ヲオモフ
端ナクモ更ニ桑乾ノ水ヲ渡リ
カヘッテ并州ヲ望メバ是故郷
桑乾は即ち多摩川に相当する。多摩川(六郷川)を渡り川崎宿に足を入れた芭蕉が、十年暮らした江戸を振り返り、そこを故郷と吟じたのである。 この句の碑が芭蕉没後三百年の年に、彫刻家圓鍔勝三氏の揮毫により旧川崎宿鎮守稲毛神社に建てられることは洵に時人所を得たことである。 なお、この十年後、芭蕉は八丁畷で「麦の穂」の句を残している。芭蕉と川崎の縁の深さが思われる。
平成六年一二月 飯塚 秀吉
この句は、『甲子吟行』(巻頭句が「野ざらしを心に風のしむ身哉」であるところから一般に「野ざらし紀行」として知られる)の2番目の句である。 飯塚秀吉氏は県立川崎中学の第1期生。文学者・歌人・芭蕉 の研究家で、長く母校で教鞭を執られた。氏はかねてから、この句は芭蕉が江戸出立の時に詠んだのではなく、多摩川を渡って川崎宿に入ってからのものである、と主張しておられた。
圓鍔勝三氏は、長年川崎市中原区にお住まいの彫刻家で文化勲章受章者。 平成6年10月、飯塚氏の病の重いことを知った教え子たちは、芭蕉没後300年のよき年でもあるので、句碑を建立して恩師を励まそうと、川崎市俳句協会の協力、260余名の協賛を得て本碑を建てた。同年12月23日、飯塚氏は自ら元気に除幕された。そして、丁度ひと月後の翌年1月23日、逝去された。享年80歳であった。
田中丘隅ゆかりの手洗石(川崎市指定文化財)
この手洗石は、田中休愚(丘隅)が勘定支配格に就任した享保14年(1729)に、彼の一族と手代衆らによって、川崎宿の鎮守であった山王社(稲毛神社)へ奉納されたものです。
田中休愚(1662~1729)は、江戸時代中頃の人で、大著『民間省要』を著し、民政に大きな業績をあげたことで知られています。また、彼は川崎宿の本陣職を努め、衰退していた川崎宿の立て直しや二ケ領用水の改修などを成し遂げたことでも有名です。
この手洗石は、田中休愚の活躍の舞台であった川崎宿に残された数少ない資料として貴重な価値をもっています。なお、この手洗石の正面には、これを奉納した五人の名前が力強い文字で刻み込まれています。
田中仙五郎は休愚の次男、田中團助は休愚の縁者であったと思われます。森田重郎衛門、富永軍治、角田半四郎の三人は休愚が行った土木治水事業の技術者として当時の文献にもしばしば登場しています。
川崎市教育委員会は昭和六十三年十一月二十九日、この手洗石を川崎市重要歴史記念物に指定しました。
平成三年三月 川崎市教育委員会
御神木大銀杏と十二支めぐり
 御神木大銀杏
御神木大銀杏稲毛神社の御神木大銀杏は、樹齢一千年以上といわれ、稲毛神社の長い歴史と尊い由緒を物語っています。
江戸時代には東海道を旅するものに「山王様の大銀杏」として知られ、安藤広重の『武相名所旅絵日記』などに当時の神々しい姿が描かれています。また別の書物(『禺老忠政遊覧記』)には「この大銀杏の周囲を回りながら願い事をすると、ことごとく叶う。特に縁結び、子授け、子育て、学問稽古事の向上に霊験があり、参拝者がたえない」と書かれています。さらに、 “いろ紙に願い事を書いて枝に結び、一葉をとってお守りにするとよい”と伝えられています。
戦前は神奈川県指定の天然記念物でしたが、惜しくも昭和20年の戦火により大きく損傷してしまいました。しかし、年とともに蘇り、その生命力の強さは御神霊のなせるわざと、人々はいよいよ篤い信仰を寄せています。と同時に、近年“平和のシンボル”としても仰がれるようになりました。
昭和61年、稲毛神社境内整備事業の一環として、この御神木の周囲に十二支のブロンズ像(制作・川村易)を置き、「十二支めぐり」として整備しました。ご自分の生まれ年の像を通して御参拝下さい。なお、根元の祠は竜神様です。












大鳥居

社殿前の石の鳥居の台座には、江戸時代の川崎宿の有力な旅籠や商人の名が刻まれており、歴史的価値の極めて高いものです。 江戸時代末期の古文書『当宿山王宮由来之事』(森家文書)によれば、
- 享保3年(1718)石之大鳥居建立 右兵庫(田中丘隅)其筋え御願申上候処格別之御勘弁を以かぶき芝居興行 舞台等殊之外大造りニいたし桟敷ナド二重ニ掛け〈略〉其賑敷事人々ノ目を驚かし〈略〉存之外余金宜敷諸入用存分ニ相拂残金を以石之大鳥居相建 凡金六十余両相掛り其外余金有之候間 金百余両末々修理之ためかし金ニいたし置候処惜哉元文ニ至り故障あって失之〈略〉右大鳥居之儀者安政二卯年(1855)10月二日之夜四ツ半時古今稀成大地震ニ而倒れ大損し今者無之候
- 嘉永二年(1849)宿役人並下役一同打ち揃い石之大鳥居を建立 諸雑用共凡百両余掛候 尤も外ニ者一銭も勧化いたさず頼母子講立候
1. の鳥居がこの鳥居です。そして倒壊してしまった1. の鳥居の台座と思われるものもそばに置いてあります。田中兵庫の名が見えます。なお、この鳥居については、台座と柱の石質が違うところから、台座は1 .のもの、柱は2. のものではないかとも考えられています。 また、「川崎宿問屋日記」の弘化二年(1847)五月十五日に 当宿六郷川御普請所足金無尽取立ニ会目連中ヨリ貰請候高金百八 拾両也 此金ニ而山王鳥居建立 とあります。
御神水吹上井戸石枠

かって、川崎は水が悪く、住民は長い間たいへん苦労しましたが、この井戸だけはいつもこんこんと清水が湧いていました。住民たちはこの井戸を「吹上井戸」と呼び、鎮守のお恵みとして大切にしておりました。特に、流行病のときなど、水垢離をする人が遠くからも来たということです。しかしその清水も工場による地下水の汲み上げのためか、昭和の初期に枯れてしまいました。
この石枠は川崎宿の旅籠屋中の寄進によるもので寄進者の名が記されていますが、文化八年(1811)と文政一二年(1829)の二つの年号が刻まれています。勧進に19年もかかったのでしょうか、それとも、文化年間にできたものが破損したか不都合があって文政12年に造り替えたのでしょうか。
小土呂橋遺構

小土呂はいまの小川町で、この橋は東海道が新川堀(いまの新川通)を横切るところにかけられていました。橋脚には下のような銘文があります。
新川堀は慶安3年(1650)に幕府関東郡代伊奈半十郎忠治が普請奉行となって開削されましたが、そこに架けられた小土呂橋の最も古い記録は、正徳元年(1711)に代官伊奈半左衛門によって板橋として造られたというものです。その後、享保11年(1726)に田中丘隅(兵庫)が石橋に改ため、それが寛保2年(1742)の洪水で大破し、翌年に幕府御普請役水谷郷右衛門によって再興されたのがこの橋です。
以来この橋は昭和7年(1932)に新川堀もろとも埋められるまでおよそ200年間、多くの人々に利用されてきました。 銘文中の左兵衛は当時の名工六郷八幡塚村の永井佐兵衛、仕手吉六は鶴見橋そばの飯島吉六と思われます。何代かあとの吉六の名は前出の大鳥居の台座にも見られます。元請けが佐兵衛、実際の仕事を吉六が行ったもののようです。
この遺構は昭和61年、旧川崎宿鎮守稲毛神社の境内整備事業にともない、川崎市より譲り受け、ここに設置したものです。 小土呂橋は市内の数少ない近世石造橋の中で、その年代が最も古く、規模も大きく(3間×3間)、幹線街道に幕府御普請所が架橋したものであるため、諸種の資料によって架橋の事情や構造が判明することから、高い資料性をもっています。 この橋をかつて、歴代の将軍や大名が通り、オランダ、朝鮮、琉球の使節が渡り、ハリスも勝海舟も、象さえも通ったかと思うと感興はつきません。
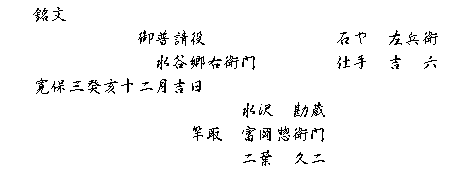
正岡子規没後100年記念句碑

俳聖正岡子規の没後百年に際し、川崎を詠んだ子規の句から
六郷の 橋まで来たり 春の風
を撰び、川崎の文化碑として後世に伝える事にした。
正岡子規本名常規幼名升は慶応 3年 9月17日(1867)松山藩御馬廻番の家に生まれ、松山中学から政治を志して叔父加藤拓川(のちベルギー公使 松山市長)を頼り上京、帝国大学予備門に合格、帝国大学文科に進学した。
22才の時に喀血し以後子規と号した。 叔父拓川の親友日本新聞社主 陸羯南(くがかつなん)の知遇を得、25才で同社記者となり日清戦争に従軍するも、大喀血し病床についた。脊髄カリエスで歩行困難となり、不治の病と闘いながらも「病床六尺」などの優れた随筆・評論を書き続け、明治35年 9月19日35才の短い生涯を閉じた。
本句は国会図書館所蔵の、寒山落木巻三(明治27年)春の風連句の一句で、子規の直筆そのままを句碑とした。 子規は明治27年春秋と明治33年に川崎を訪れ、大師詣での道すがら多くの句を詠んでいる。
川崎や 畠は梨の 帰り花
川崎や 小店小店の 梨の山
多摩川を 汽車で通るや 梨の花
麦荒れて 梨の花咲く 畠哉
百舌鳴くや 晩稲掛けたる 大師道
朝霧の 雫するなり 大師堂
いずれも果物好きの子規らしい句であると同時に、米麦農業から果樹農業への転換を図った当時の川崎を知ることができる。 短い生涯の最後の血一滴まで、文芸革新の道を追求した子規の情熱に敬意を表しここに句碑を建立する。
大川崎宿祭実行委員会
代表 斎藤文夫 稲毛神社 宮司 市川緋佐麿
近代の俳聖正岡子規が明治35年9月19日、35歳で早逝してから本年は丁度百年に当たり、しかも野球の普及につとめ、自ら野球(のぼーる)と称し、打者・走者・飛球など現在使用されている野球用語を考案し、発展に貢献された人として、野球殿堂入りした記念の年でもあります。
子規は明治27年の春と秋、明治33年にも川崎を訪れ、大師詣の道すがら梨や麦畑の続く、当時の川崎の情景を数多く詠んでおります。
この度中島八幡神社境内に 「多摩川を 汽車で通るや 梨の花」 の句碑が建立されるのに呼応して、平成13年5月挙行いたしました「大川崎宿祭り実行委員会」が、稲毛神社境内に子規の句碑建立を発願いたし、国会図書館が所蔵している子規の明治27年作「寒山落木」(巻三)の中の「春の風」連句の中から、川崎にかかわる 「六郷の 橋まで来たり 春の風」 の明るい句を撰び、子規の直筆を本小松の自然石に刻みました。 郷土の誇る詩人佐藤惣之助の詩碑の隣りに、建立させて頂きましたが、この二つの文化碑が、香り豊かな文化の街川崎の表徴となるよう期待してやみません。
正岡子規は、明治の中期に両三度川崎を訪れ20数句を残している。 それらの句の多くに梨が詠み込まれていて、当時の川崎の名物が果物であったことが伺える。
他方江戸時代には、芭蕉の「麦の穂」の句碑や、川崎宿名物の一つが麦藁細工であったこと、さらには、稲毛神社の「古式宮座式」(県文化財)の秘伝のお供え物は麦を調理したものであることなどから、川崎は麦の里であることが知られる。
維新前後、川崎は東京・横浜の後背地として米麦から換金作物としての果樹栽培に転換する。文明開化で手に入りやすくなった外国種を取り寄せ、積極的に新種の開発に当たった。その結果、明治26年(1893)には大師河原村の当麻辰次郎が「長十郎梨」を、明治29年には大島村の吉沢寅之助が「伝十郎桃」を生み出すなど、次々と優れた品種が開発された。
しかし、明治末期からの工場誘致により大正中期には酸毒(公害)により枯死が目だつようになる。だから子規の句は麦から果樹への転換を図って懸命に努力した川崎の一時代を映している。
この度の句碑の句も、川崎に新しい風が吹き込まれ始めたことを謳っていて希望に溢れている。川崎の文学碑としてまことにふさわしく、関係者の一人として嬉しい限りである。